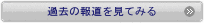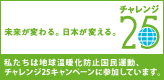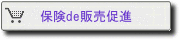平成22年4月13日(火)9:50~10:11 場所:金融庁大臣室
[記者質問]保険毎日新聞の園田です。
公益法人が約2万5,000(団体)ある中で、共済事業をやっているところが2,000(団体)ぐらいあると聞いていて、かんぽ(生命保険)の改革が進められる中で、かんぽ(生命保険)も、簡易保険加入者協会で、共済(事業)を別の形でやっていると聞いているのですけれども、「今回の新法で、そういうところも保険事業として認め(られ)る方向にあるのかどうか」ということを、結構、所管の方達とかがすごく気にされていらっしゃるので、その辺の方針のお考えをお聞かせください。
[大臣]今、これは、中身については、今、大塚副大臣のもとで検討しているところですけれども、基本は、もう善意で零細な組合が相互扶助というようなことでやってきたのが、事業継続できなくなっているところがたくさん出ているのです。そういうことをなくそうと。それは、中には、契約者の立場で(見て)も「大丈夫かな」というようなところがあるかもしれないですけれども、かつてのオレンジ共済みたいな、悪意が固まっている(団体)ばかりというわけではないので。善意でやっているところがほとんどなので、そういうところまでやっていけなくなるようではいかんので、急いで。放っておいたらそうなってしまいますから。今国会でそれをやるということで、大塚副大臣のところでやってくれている最中です。
[副大臣] そこは、また追々ご説明します。今、おっしゃったのは、ちょっと最後のところが聞き取れなかったのですけれども、かんぽ(生命保険のこと)ですか。何とおっしゃったのですか。
[記者]簡易保険加入者協会です。何か、火災保険とか、保険事業をやっていて...。
副大臣) ちょっと、そこについて、今、検討している延長線上でカバーされているかどうか、確認してみます。
平成22年4月9日(金)13:41~14:16 場所:金融庁大臣室
[質問]保険毎日新聞の園田です。
来週、共済の新法の素案が出るという情報を得たのですけれども、その柱みたいなものをどういうふうに考えていらっしゃるのかということを、消費者保護をどういうふうに担保するのかという観点から教えてください。
[大臣]これは、残念ながら、この間の法律(保険業法)の改正で、今、特に中小の共済でお互いに助け合ってやっている方々が事業継続できないという状況に追い込まれてきてしまっていますから、そういう、お互い助け合いの共済が継続して事業ができるように法律上でちゃんとやっていくと。(ただし、)共済の中には、加入者、契約者の利益というのが大丈夫かなという経営というか、それをやっているところがあることも事実なのです。かつて、オレンジ共済みたいなことがありましたけれどもね。だから、そういうことが起きないで、規模が小さいところもちゃんとやっていけるような...。あなたたち(大塚副大臣、田村大臣政務官)がやってくれているのでしょう。大体、最終段階くらいで、まだちょっと、私も法律(案)そのものは見ていないのですけれども、「そういう方向で法律を作ってくれ」ということで。私はあほですけれども、大塚(副大臣)君と彼(田村大臣政務官)が、今、私の意を体してやってくれておりますから。これは、土台は4月中にできるのですか。
[政務官] 法案自体は4月中...。1日も早く、ということで作業しています。
[大臣]これは、急いでやらないと潰れてくるところ出てくるのですよ。急いでやります。
平成22年4月6日(火)10:40~10:58 場所:金融庁大臣室
[質問]保険銀行日報の片岡です。
先週の金曜日、共済関係8団体と懇談をしたと思うのですが、その趣旨、狙いと、話し合った結果どのように感じられたか、お話し願えれば。
[大臣]やはり、(先の)保険業法の改正で、結局、いわゆる「お互いに助け合う」というような形の中でやっておられた小さな共済組合が存続できなくなるという、現実のいろいろな問題が出てきたので...。やはりお互い助け合っていくということ自体はね、それぞれの組織がありますね、組織単位でそういうことをやっていることはね、共助という面では、私は、良いことだと思うのです。やはり、それができなくなるということは良いことではないので、そういうことが可能な...。しかし、かつてのオレンジ共済とか、そういうようなことの中で、加入者が食い物にされたというような事態も起きたわけですから、そういうことが起きたら困るわけですから、やはり、そこらを含めて加入者がきちんと保護される、守られるという、また、その理念、利便性を考えながら、小さい共済でもちゃんと継続してやっていけるような方向で検討したらどうか、ということで、今、大塚副大臣と田村(大臣)政務官に検討をしてもらっている最中ですが、4月中には法律案ができると思います。
 株式会社インタークルーはお陰様で15周年を迎えました。
インタークルーは保険業等に特化した経営コンサルティング会社です。
株式会社インタークルーはお陰様で15周年を迎えました。
インタークルーは保険業等に特化した経営コンサルティング会社です。